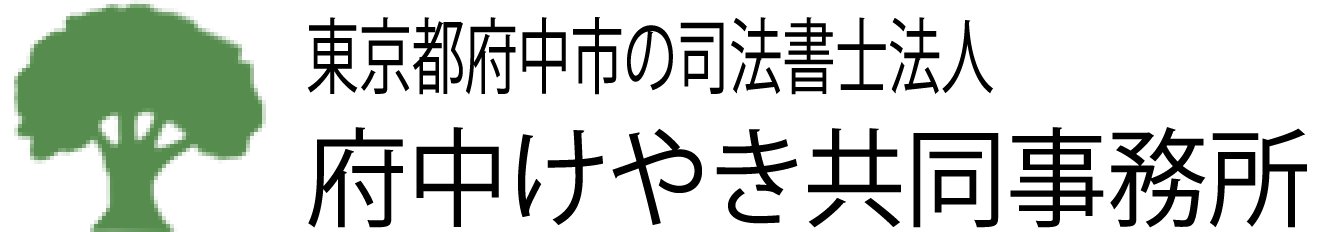ブログ

2019/12/11
自筆証書遺言の方式緩和
こんにちは!
司法書士法人府中けやき共同事務所の秋池です。
久しぶりの更新となってしまいましたが、当事務所も法人化をきっかけにより多くの方へ法律知識や、登記・相続・供託についての情報を
わかりやすくお届けしたいと思い、ブログという形で情報発信を行っていくことに致しました。
法律関係の解説と聞くと専門用語満載で難しそうなイメージもあるかと思いますが、なるべく専門用語を使わず、
わかりやすい解説を心がけてまいりますので、お付き合いいただければ幸いです。
さて、今回のブログでは相続に関する法改正がありましたので、その解説をしていきたいと思います。
中でもすでに施行されている自筆証書遺言の方式緩和について解説していきます。
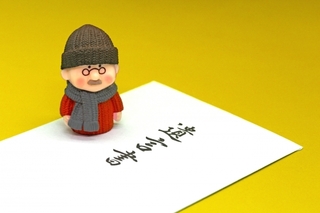
なぜ変わるのか?
2018年7月6日に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が国会で成立し、7月13日に公布されました。
(公布とは「こんな内容の法律ができました。または変わりました。なので皆さんにお知らせします」ということです)
この後、原則として公布の日から1年以内に施行(法律の効力が発生することです)されることとされていますが、
(配偶者の居住の権利については2年以内です)自筆証書遺言の方式緩和については、2019年1月13日から施行されています。
法改正についてはニュース等でも報道されているのでご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか?
特に、配偶者の居住権を保護するための方策に関しては大きな注目を集めているように感じます。
こちらの施行は2020年4月1日ですのでもう少し先になりますね。
今回の法改正は約40年ぶりの相続に関する民法の改正なのですが、2013年9月に最高裁判所において嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1と定めていた規定が憲法に違反するとの決定がされたことがきっかけです。
*嫡出でない子とは法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子。
*嫡出子法律上の婚姻関係にある男女=夫婦の間に生まれた子。
憲法というのは法律の世界の絶対です。つまり憲法に違反している法律はそもそもダメです。
ですので、上記決定がされた後法務省では「憲法に違反しているのだから2分の1の規定は削除しましょう」ということになり、
国会に提出しようとしたのですが各方面から「影響が大きいことだし、配偶者の保護も考えないといけませんよね」という問題提起があり、
相続法制検討ワーキングチームを設置してどのように法律を変えればより国民のためになるだろう?という検討がスタートしました。
その後の時系列は長くなってしまうので省きますが、検討に検討を重ねた結果今回の改正に至ったわけです。
遺言ってどう書くの?
注目度の高い配偶者居住権の保護に関しては施行までまだ時間がありますので、
先にも述べた通り今回は自筆証書遺言の方式緩和について解説していきます。
遺言にも種類があり、今回解説する自筆証書遺言は書き方の種類の一つとなります。
まず大きく分けて普通方式遺言と特別方式遺言とに分かれますが、
特別方式遺言は文字通り特別な時(船や飛行機の事故にあってしまい助からない時など)ですので、
一般的な普通方式遺言の種類は3つあります。
①公正証書遺言
遺言を残したい人が公証人という人に口頭で内容を伝え、公証人が作成し、公証役場というところで作成します。
作成の際には証人2名と手数料が必要です。証人は遺言を残す人の子どもや遺言によって財産を受け取る予定の人はダメです。
作成した遺言証書は公証役場に保管され、遺言を残した本人には正本(原本と同じ効力を持つもの)が渡されます。
費用はかかりますが、確実性の高いものですね。
②秘密証書遺言
公正証書遺言と同じく公証役場で作成しますが、内容を秘密にできます。
亡くなるまで遺言を誰にも知られたくないという方は利用しますが、弊所への相談ではあまり多くありません。
③自筆証書遺言
今回方式が緩和されたのが、この自筆証書遺言です。
自分で紙に書いて、日付と名前と押印を忘れずに行い、封筒に入れて糊付けして、
出来れば糊付けしたところに本文で押した印鑑と同じものを押して(封印)自宅で保管します。
遺言を書いた方が亡くなった後発見した家族は家庭裁判所で検認を必ず受けなければなりません。
変わったところ
これまで自筆証書遺言は全文を手書きで書かなければいけませんでした。
全文を手書きしなければいけないため、大きな労力のかかることだったのですが、
今回の改正で財産に関しては目録をパソコンで作成しても良いことになりました。
また、預金に関しては通帳のコピーを添付しても良いことになりました。
以下参考までに自筆証書遺言の例を作成しました。
上記遺言書はすべて手書きする必要があります。
そして絶対に忘れてはいけないところが、日付・名前・押印です。
遺言書の中で出てくる別紙も以下に例を作成しましたので参考にしていただければ幸いです。
別紙1と2はパソコンで制作する、またはコピーした紙そのものを使用しても構いませんが、
必ず署名と押印が必要になります。コピーしたそのままの紙を別紙にする場合は必ず別紙と書いてくださいね。
今回の例では別紙1に残したい土地の情報をパソコンで記載していますが、登記簿謄本でも代用は可能です。
登記簿謄本はお近くの法務局で取得することもできますし、司法書士へ取得を依頼することも可能です。
残したい土地についての目録を登記簿謄本で代用する場合も通帳コピーと同様に必ず別紙〇(←番号)の記入と署名・押印が必要となります。
また遺言書(手書きの物)は別紙の余白に書いてはダメです。
必ず一枚の紙に上記例のように記載する必要があります。別紙はあくまで別紙ですので、間違いないように注意したいですね。
もう一つご注意いただきたい点が、目録をパソコンで作成した場合全ページに署名押印が必要となりますので、
両面印刷をした場合は両面共に署名押印が必要となります。
いかがだったでしょうか?
全文を手書きしなければいけなかった自筆証書遺言が改正によって、一部ではありますがパソコンの使用も認められるようになりました。
より遺言を気軽に作成できるような時代になりましたが、大切なことは遺言書を作成する前に自分の財産がどのくらいあって、誰に何を残すかをきちんと把握することにあります。
人によって様々ですが、長いこと働いて築いた財産です。どう使っていってほしいかも含めて考える必要がありますね。
また、自筆証書遺言には先に解説した検認という作業もありますので、もし発見した方は勝手に中身を覗いたり、絶対にダメですが書き換えてしまったりはしないようにお願いします。
弊所では遺言についてのご相談も受け付けておりますので、どのタイプの遺言を選択すればよいかわからない。
といったお悩みや、そもそも遺言を書いた方が良いのか?といったお悩みまで皆様の次世代に残したいという気持ちを大切にご相談にお乗りしています。
どうぞお気軽にご相談ください。
相続法改正については順次解説してまいりますので、今後とも弊所並びに当ブログをよろしくお願いいたします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
- 住所
- 東京都府中市寿町1丁目8-8-701
※駐車場有 - 業務時間
- 月〜金 9:00〜18:00
※2024年より変更いたします。 - 最寄駅
- 最寄駅:京王線府中駅
- 電話番号
- 042-334-2700
司法書士法人府中けやき共同事務所